めっきのひろば > ロジウムめっきとは?
ロジウムめっきとは?
はじめに
ロジウムメッキは、装飾品から電子部品・光学機器まで幅広く利用されています。しかし、「他のメッキとどう違うのか」「設計や依頼に不安がある」と感じている方もいるでしょう。ロジウムは希少金属であり、その輝きや耐食性・耐摩耗性は高く評価されていますが、下地金属の選定や工程管理を誤ると性能を十分に発揮できないケースもあります。
当記事では、ロジウムメッキの基礎知識や用途、特徴、加工工程などを分かりやすく解説します。ロジウムメッキに関する知識を整理することで、導入や加工の可否をより的確に判断できるようになるでしょう。
三ツ矢のロジウムめっきはこちら
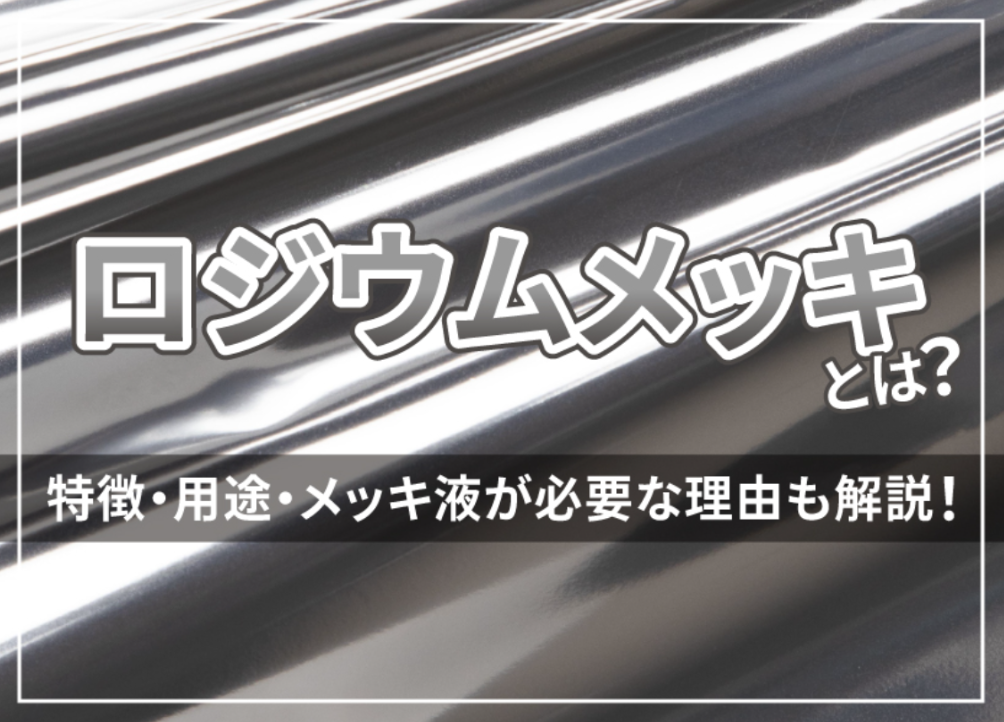
ロジウムメッキとは?
ロジウムメッキとは、 貴金属の一種であるロジウムを金属表面に薄く被覆する表面処理のことです。銀白色の強い輝きと高い硬度を持ち、酸化や変色に強いため、装飾品から電子部品まで幅広い分野で活用されています。
ジュエリー業界では「プラチナ仕上げ」や「ロジウムコーティング」として知られることも多く、耐食性や耐摩耗性を向上させる役割も担います。通常はニッケルやパラジウムを下地に施した上で、0.05~0.3μm程度の薄い層を形成するのが一般的です。
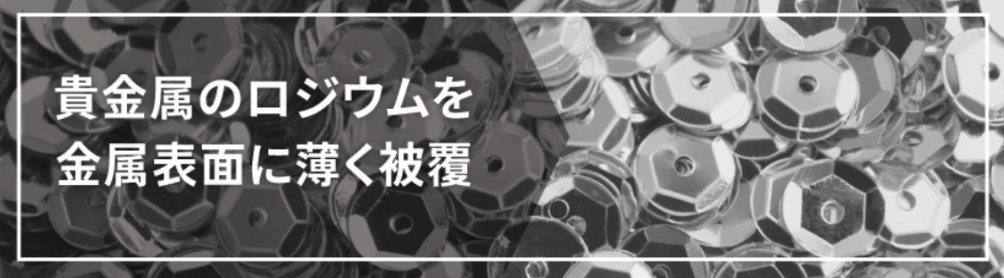
ロジウムメッキの主な用途
ロジウムメッキは、その強い耐食性や耐摩耗性を生かし、装飾用と工業用の両面で幅広く利用されています。品分野では、ネックレスや指輪などのアクセサリー、眼鏡、時計、楽器などに施され、銀に代わる輝きと変色防止の効果を発揮します。
一方、工業用途では、 摺動や磨耗の激しい接点部や電子部品、リードスイッチ、テストプローブの接触子などに利用されるほか、反射特性を生かして光学機器や音響部品にも採用されています
ロジウムメッキにメッキ液が必要な理由
ロジウムメッキは電解メッキの一種であり、ロジウム化合物を溶かしたメッキ液中で電流を流し、金属表面にロジウムを析出させます。この メッキ液を介することで、複雑な形状の部品にも均一かつ極薄の膜を形成できるのが特徴です。
一方、PVDなど液を使わない方法は「コーティング」に分類されるため、厳密にはメッキとは異なります。そのため、ロジウムメッキを実現するには専用のメッキ液が不可欠です。
ロジウムメッキの特徴
ロジウムメッキは、さまざまな特性を備えています。代表的な特徴としては、以下が挙げられます。

・耐食性
ロジウムは化学的に安定しており、酸やアルカリ、塩水などによる劣化を受けにくい性質を持ちます。そのため、腐食や変色を防ぎ、メッキを施した製品の寿命を延ばします。ジュエリーや時計など、日常的に使用される製品に適した特性です。
・耐熱性
高温環境でも安定した性能を維持できるのがロジウムメッキの強みです。熱による変質や変色が起こりにくいため、工業用部品や電子機器などの過酷な条件下でも評価されています。
・電気伝導性
ロジウムは良好な導電性を持つため、電子機器や精密部品の接点に利用されます。導電性と耐食性を兼ね備えていることで、長期にわたり安定した性能を発揮できます。
・耐摩耗性
Hv800~1000という高い硬度を誇り、摩擦や衝撃による摩耗に強いのも特徴です。日常的に擦れや衝撃を受けやすいリングや眼鏡フレームのほか、可動接点などにも適しています。
・反射率
ロジウムは光を強く反射し、銀白色の美しい光沢を持ちます。この特性は装飾品を華やかに見せるだけでなく、光学機器や車両の反射板、医療用ミラーなどでも利用されています。
これらの特性により、 ロジウムメッキは「美観性」と「機能性」を両立させる表面処理として位置づけられています。装飾用途だけでなく、電子部品や光学機器といった実用分野でも、その信頼性の高さが支持されています。
ロジウムメッキの加工工程を解説
ロジウムメッキは、高品質な仕上がりを実現するために複数の工程を経て行われます。ここでは、前処理からメッキ処理、後処理までの流れを分かりやすく解説します。

①前処理(洗浄・下地づくり)
ロジウムメッキを行う前には、基材の表面を徹底的に整える前処理が必須です。研磨や酸洗浄、アルカリ洗浄によって油分や酸化物、汚れを除去し、金属表面を清浄にします。 前処理によりメッキ層の密着性が高まり、剥離や不具合を防止できます。
さらに、ロジウムを直接施すのではなく、ニッケルやパラジウムなどの下地メッキを施すことで、より強固で安定したロジウム層を形成できるようにします。
②ロジウムメッキ処理
前処理を終えた製品は、ロジウムを含む電解浴に浸され、電解メッキによって表面に薄いロジウム層が析出されます。対象の金属は陰極として接続され、電流を流すことで溶液中のロジウムイオンが還元されて金属表面に付着します。
メッキの厚みは処理時間や電流密度により調整され、通常0.05~0.3μmほどの非常に薄い層を形成します。この工程によって、 均一で光沢のある仕上がりが得られ、装飾性と機能性を兼ね備えたメッキが完成します。
③後処理と仕上げ(洗浄・検査)
ロジウムメッキが施された後は、 表面に残った溶液を洗浄し、必要に応じて乾燥や熱処理を行い、耐久性や仕上がりを高めます。その後、外観検査で傷やシミ、剥がれがないかを細かく確認します。
検査に合格した製品は、梱包後に出荷されます。後処理と仕上げは見た目の美しさだけでなく、長期的な耐久性や信頼性を確保するために重要な工程であり、装飾品から工業部品まで高い品質を維持するためです。
ロジウムメッキのよくある質問
ロジウムメッキは装飾分野から工業分野まで幅広く利用されていますが、導入を検討する際は「アレルギーリスクへの影響」「コスト面・加工上の課題」など、実務に直結する疑問が多く挙げられます。ここでは、代表的な質問に答えます。
Q.ロジウムメッキは金属アレルギーになりやすい?
A. ロジウムは化学的に安定しており、アレルギーを起こしにくい金属とされています。そのため、金属アレルギーを持つ人でも使用できると言われています。ただし、実際の加工ではロジウムだけを直接施すのではなく、下地にニッケルやパラジウムを用いるのが一般的です。
ロジウムメッキの下地に使うニッケルやパラジウムは金属アレルギーを引き起こしやすく、メッキが摩耗して下地が露出した場合に症状が出る可能性があります。特に、ニッケルには注意が必要です。メッキ加工を検討する際は、下地に使用する金属の種類を事前に確認するのが望ましいですが、実際の取引や仕様書だけでは正確に把握できない場合もあります。そのため、まずは交換可能な部品や試験サンプルで評価するとよいでしょう。
Q.ロジウムメッキにはデメリットもある?
ロジウムメッキの大きなデメリットはコストの高さです。 ロジウムは希少金属で価格が高騰しやすく、製品の生産コストや販売価格に影響します。また、メッキ層が非常に薄いため、摩耗や剥離で下地が露出すると、変色や劣化のリスクが生じる点にも注意が必要です。装飾品では、ロジウムメッキにより素材本来の色味や質感が隠れてしまう場合もあります。
しかし、ロジウムメッキのデメリットによる課題には対策が可能です。たとえば、適切な使用環境や定期的なメンテナンスによってメッキ寿命を延ばすことができます。部品や製品用途に応じて下地金属を選定すれば、腐食やアレルギーリスクも抑制できます。高コストでも、高級感や耐久性を求める用途では十分な価値を発揮するのがロジウムメッキの強みです。
まとめ
ロジウムメッキは、耐食性や耐摩耗性、反射率など、多くの優れた特性を持ち、装飾品から電子部品・光学機器まで幅広く活用されているメッキ表面処理です。均一で美しい仕上がりを実現するには、ロジウムメッキ液を用いた電解メッキが不可欠であり、工程ごとの管理が品質を左右します。
一方で、高コストや下地金属に由来するリスクなどの課題も存在しますが、適切な材料選定やメンテナンスによって十分にカバーすることが可能です。今後の製品開発や加工依頼にロジウムメッキを取り入れることで、競争力のあるものづくりに結び付けられるでしょう。
ロジウムめっきに関するお問い合わせはこちら










